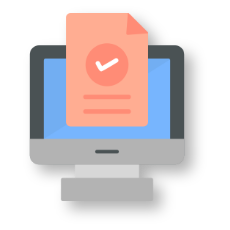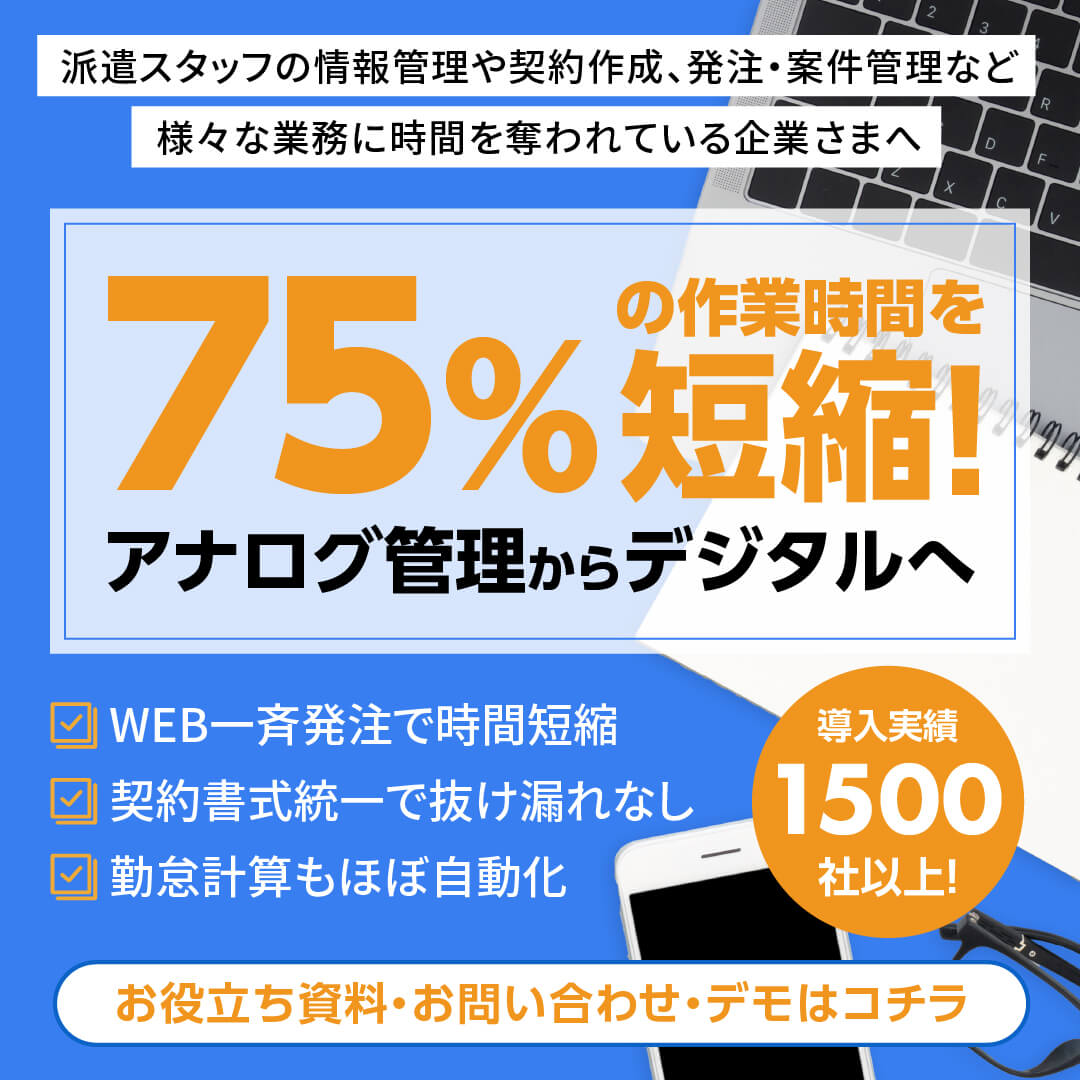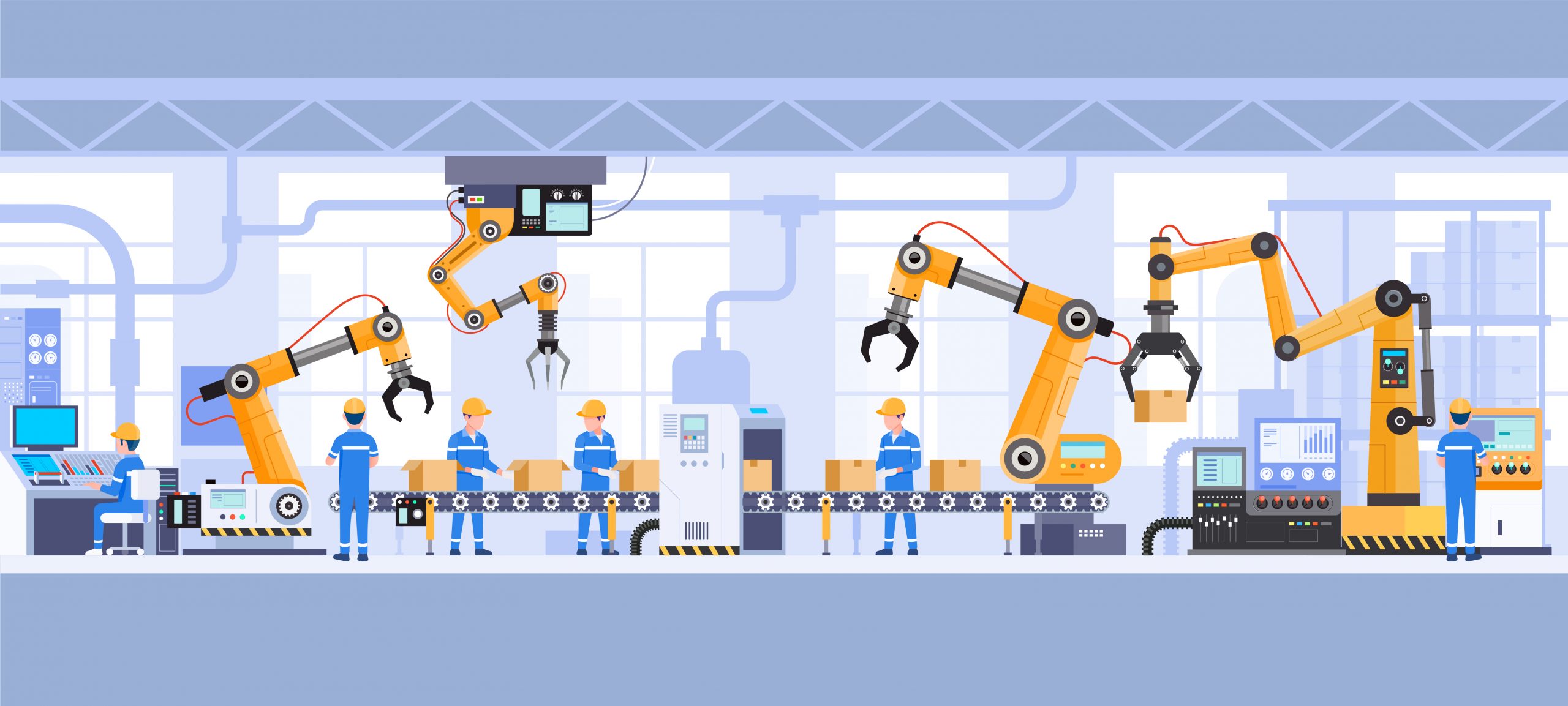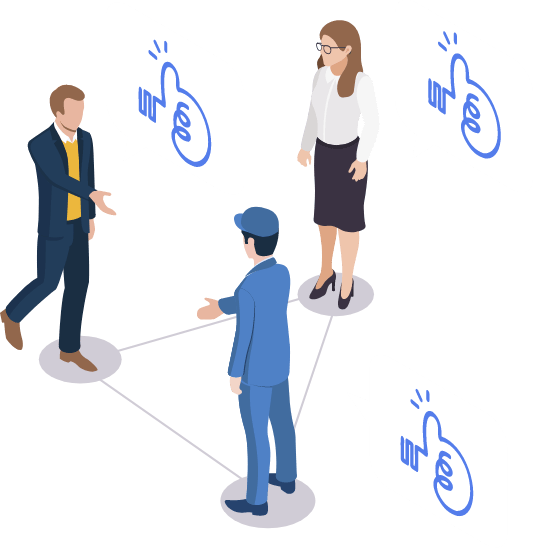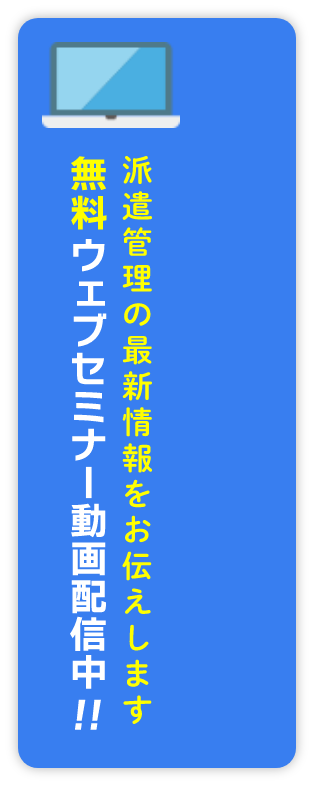派遣社員の評価って派遣先がやらないといけないの?派遣料金にも影響が?
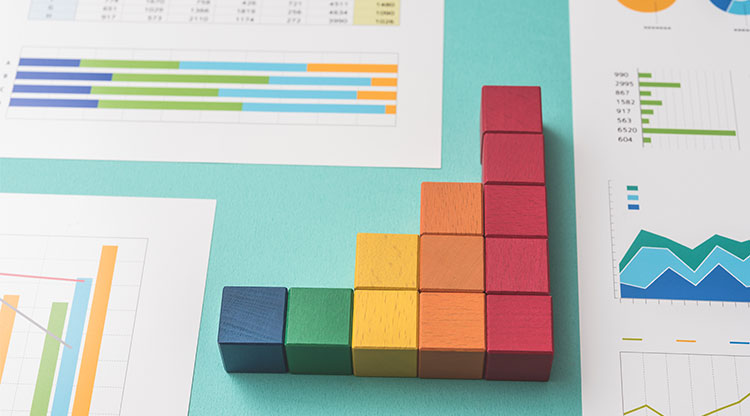
年末も迫ってきている中、企業様からこのような声が届いています。
「同一労働の関係で派遣元から『派遣社員の評価をしてくれ』って言われるけど、労使協定方式なのに、派遣先がやらないといけないの?」
そうですよね。労使協定方式だから、派遣元の問題じゃないか?となりますよね。
答えとしては仰る通り、
「やらなくてよい。義務があるのは派遣元。」 となります。
ただアドバイスをするとしたら、「やったほうが良い。」とお答えします。
関連記事:派遣社員の同一労働同一賃金、何が起こる?―次年度に向けた賃金、派遣料金の見直しはあるのか―
というのも、派遣元が派遣社員(自社の雇用する社員)を評価し、賃金を見直すことが義務づけられていますが、派遣先にもそれに対して「配慮義務」が設けられています。
「配慮義務って何?」と思われるかもしれませんが、簡単に言うと「派遣料金が適正になるように、派遣元に協力しなさい」というところになります。
「適正な料金」と言っても、何に対しての適正なのか?
そもそも20年4月で料金見直しを行っているのに・・・ という声も聞こえてきます。
今回の法改正では派遣元に、1年間に1回派遣社員の評価を行い、その能力などの向上により料金の見直しを行うよう定められています。しかし派遣元が実際のスキル向上などを直接判断することが難しいため、派遣先に協力を依頼してくることになります。
ここでご注意いただきたいのが、労使協定では職種ごとに賃金テーブルが定められることになり、本来はそのテーブルの設定については時間をかけて行われるべきところ、昨年2月後半からコロナウイルスの問題~休業という流れになってしまい、派遣元も十分な時間を取れず労働局に提出をしているところが多いと思われます。(提出といっても審査があるわけではないのですが、確認はされていると思ってよいのではないでしょうか)
その賃金テーブルも厚生労働省が参考に出したものに従って作られていると、1年経過した場合はスタート賃金から約16%、丸3年経過では31%ほど上がったものになっています。安易に料金を見直しましょうとは言いにくいテーブルになっている可能性があるということです。
また厚生労働省のQ&Aに、「評価は公正に行われるべきで、賃金が上がらない(または下がる)ことが前提で行われてはならない」旨の記載があります。そのあたりが適正に行われていないと判断された場合、労使協定が履行できていない=均等均衡方式で派遣をしなさいという流れになります。
説明が回りくどくなりましたが、つまりは、評価結果が「派遣料金」として、派遣先に影響してくる可能性が高いということです。さらに複数の派遣会社をご利用されている場合は、派遣会社ごとに賃金テーブルや評価項目が異なり、それぞれ対応する手間が大きくなるでしょうし、あまりに差があるとスタッフ間でのトラブルにつながる恐れもあるのではないでしょうか?
そのため評価項目や昇給について各社ごとの対応とならないよう、派遣先としては極力統一できる状況を作ることが有効だと考えられます。
これから年度末にかけて各派遣元からの依頼も増えることでしょう。一度自社の状況を確認してみてはいかがでしょうか。